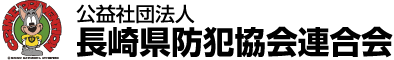犯罪の予防と対策
■特殊詐欺 ■子供の犯罪被害防止 ■「犯罪なく3ば!」運動
長崎県内における刑法犯の認知件数は、平成15年以降減少し安全安心度は高まっていますが、更に県民の皆様が犯罪の被害に遭わないために、予防と対策をしておきましょう。
特殊詐欺の被害に遭わないために
「特殊詐欺」とは、電話やメール等を使って、面識のない不特定多数の人を対面することなく金銭をだまし取る詐欺のことです。振り込め詐欺をはじめ、金融商品等の取引名目の詐欺等、いろいろな手口があります。特殊詐欺の被害者のほとんどが、犯人との電話でだまされています。
・電話の相手がお金に関する話をしたら詐欺を疑ってください。
・「うまい話」、「あわてさせられるような話」には特に注意が必要です。
①オレオレ詐欺
「オレだよ、オレ。オレ会社のお金を電車の中に置き忘れてしまって、このままだとクビになってしまう」などと、息子や孫を装ってお金を騙し取る詐欺です。
最近では、「自分では取りに行けない」と偽の上司や同僚が自宅まで現金を取りに来たり、レターパックで送らせる、指定場所に持って来させる手口も発生しています。
お金を渡してしまう前に、必ず家族や相談できる人に連絡し、一人で判断しないようにしましょう。留守番電話機能の活用や不審な電話をシャットアウトするための防犯機能の付いた電話通信機器が効果的です。最寄りの警察署生活安全課にお問い合わせください。
②還付金等詐欺
社会保険事務所や税務署等の公的機関を装って「保険料や税金の還付がある」等と嘘を言ってATMに誘い出し、携帯電話を使って操作方法を指示し、お金を振り込ませる詐欺です。
公的機関が還付金等の受取のためにATMの操作を求めることはありません。
③架空請求詐欺
「有料サイト利用料があります」「多重債務者リストに名が入っています」等、架空の話を口実として料金を請求し、お金を振り込ませる詐欺です。
裁判や差押え等の法律用語を使って不安にさせる電話やメールがあっても、一人で悩まず警察などに相談しましょう。
④融資保証金詐欺
「担保不要」「低金利で融資します」「債務の一本化を」「まずは保証料を振り込んで」などと、保証金を騙し取る詐欺です。
正規の貸金業者が融資の前に現金の振り込みを要求することはありません。うまい話には注意しましょう。
子供の犯罪被害防止
子供を守るために、親が事前に予防・対策をしておきましょう。
①ブザーの活用
子供に防犯ブザーを持たせましょう。
使い方を確認し、定期的に実際に鳴るか点検をしましょう。
②コミュ二ケーションを図る
子供が外出する際は、行き先、帰宅時間等を確認し、帰宅時間を過ぎる場合は必ず連絡するなど、家庭内のコミュ二ケーションを図りましょう。
③子ども110番の家
子どもが知らない人に話しかけられたり、不審者に後をつけられたなど、身の危険を感じたときに助けを求めて逃げ込むことができるのが「子ども110番の家」です。看板やステッカーなどの目印があります。
④安全・安心情報の活用
長崎県警察では、県民の皆様が不安に感じる情報を、「安心メール ・キャッチくん」に会員として登録された方に
- 声かけ事案等情報
子供や女性に対する声かけ事案や痴漢、不審者情報- 重要・特異事件情報
通り魔事件の発生等、重要又は特異な事案の発生に関する情報- 自主防犯活動情報
その他、防犯活動に役立つ情報- 特殊詐欺関係情報
等を幅広く配信しています。
配信には「安心メール・キャッチくん」への登録が必要です。
詳しくは長崎県警察のホームページ(暮らしの安全)をご覧ください。
「犯罪なく3ば!」運動
長崎県や警察等では、日本一安全で安心な長崎県の実現のため、県民の鍵かけをはじめとする防犯意識の高揚などを呼びかける県民総ぐるみ運動「犯罪なく3(さん)ば運動」~カギかけんばひと声かけんば見守りせんば~を推進しています。
①カギかけんば運動
住宅や車、バイク、自転車には必ずカギをかけましょう。
カギかけが、被害防止の第一歩です。
②ひと声かけんば運動
地域では、子ども達に「おはよう、おかえり」と挨拶しましょう。 あなたの「ひと声」が地域の連帯感や絆を醸成し、犯罪防止につながります。
③見守りせんば運動
地域の絆が犯罪を撃退します。防犯パトロールの促進や子どもやお年寄りを見守りましょう。